僕は冷凍ビームが打てる。
頭がおかしいと思うかもしれないが、話を聞いてほしい。
実際にビームが打てるわけではない。これは僕のあだ名だ。
僕が話すと場が静まり返ってしまう。僕自身には原因がよくわからないけれど、昔からそうだった。僕は正直気づいていなかったけれど、中学の頃に友達に言われ自覚した。
そこで友達がつけたあだ名が「フリーザー」だった。そこから「でた!冷凍ビーム!」といじられるようになり、今ではそこだけが残って冷凍ビームと呼ばれるようになった。
今はもう大学生になったが、中学、高校と続いてきたこのあだ名が今でも残ってしまっている。
最初はみんなが笑ってくれて、いじられているとしても、バカにされていたとしても、それでも嬉しかった。
でも大学生になった最近では、あからさまにズレているということを叩きつけられている感覚になり、このあだ名で呼ばれるたび、喉が細く、狭くなってしまう。
この悩みを友達や先生に相談したこともあるのだが、面白ければいいだろう、とか、そんなのみんなあるよ、気にしすぎ。だとか言われる。
僕が気にしすぎなのだろうかとも思うのだが、場が静かになるのも耐えられなくなってきているのに、そこからでたよ、と言わんばかりに冷凍ビームという言葉を浴びせられ、気が滅入ってしまう。
大学生になったらこんな事無くなる、とか、変わってやろうと思っていたが、中学、高校の知り合いも何人かおり、彼らに見つかってしまってそんな事は叶わなかった。
大学生になり、アルバイトを始めた。半年ほど経ったが、全く馴染めていない。
これで、中学からの人間のせいにしていただけで、初対面の人とも上手くやれないことを思い知らされた。
そしてまたここでも冷凍ビームと言われてしまうのだろうか、とだんだんと怖くなってきていた。
僕はアルバイト終わりに、近くの公園のベンチで音楽をしばらく聴いて、気持ちを飲み込んでから帰るようにしていた。
家族は、僕がうまくやっていると思っている。ろくに友達と呼べる存在もおらず、大学やアルバイトを息が詰まるような思いでやっていることは知らない。家族仲が悪いわけではないが、こんなこと知られたくもない。
その日も僕はベンチで座って音楽を聴いていた。許されている、とまではいかないがこの時間だけはほんの少しだけ心が軽くなる。
「おつかれー、あ、俺佐藤。誰か待ってんの?」
僕は自分に話しかけられているなどと思わなかったので一度目が合ったが、ふわふわと泳がせながら視線を逸らした。
「えっ無視?厳しいねぇ、今日バイト初めて一緒だった佐藤だよ!話には聴いてたけど初めて会えたな!同い年らしいよ俺ら!」
視線をこちらに完全に刺しながら畳み掛けるように喋りかけられ、少し怖かった。
だが僕は拒否するのもおかしいかな、と考えていた。
そうするとその佐藤、と名乗る男は隣に座ってきた。
「何聴いてたの?」
「フィッシュダイバー、だけど」
「ああー!有名な曲あるよな!あれ知ってるぜ!ニュートレジャー!」
それは僕の好きなフィッシュダイバーの看板とも言える曲だ。だが世間ではほぼこの曲しか知られていない。いわゆるこいつはミーハーだ。軽いショックを受け、もう既に喋るのが嫌になってきた。でも、話しかけられている嬉しさには抗えなかった。
「えっ?三笠?三笠大?それってあの三笠中央大学?」
彼のペースに飲まれながらも、ポツポツと話していると、同じ大学だということがわかった。そしてそこから彼は大学内でも話してくるようになった。
だが僕は相変わらず怖かった。彼も本来の僕に、コミュニケーションが致命的な僕に気づいたらすぐに何処かへ行ってしまうということが。
だから僕は頷いたり相槌を打ったり、軽いヤジを入れることしかできなかった。その中で愛想笑いだけがどんどん上手くなっていくことに対しても「これでいいんだ」と言う思いと、「なんで大学生にもなってこんなんなんだ」という思いが渦巻き常に複雑だった。
3ヶ月ほど佐藤と一緒に過ごしていた。佐藤は居なくならないかもしれない。他に友達がいそうなのに、僕とばっかり遊んでくれるのがとても嬉しかった。佐藤のおかげで大学もバイトもそれなりに行けた。
ある日、佐藤と一緒に外で昼ごはんを食べていた。一緒にいるのはとても楽だった。勝手にたくさん話してくれるし、間が生まれても埋めてくれるので空気が冷えない。その日も彼が見つけた大学近くの美味しい定食を食べていた。
「あれ?佐藤じゃん」「おお!おいすー」
彼に声をかけたのは僕を中学の頃から知る人間のうちの一人だった。
その瞬間、頭が高速で回った。そして考えてしまった。終わってしまう、やっぱり僕が誰かといるなんて許されないんだ、奪われてしまう、もうだめだ。頭の中をそんな言葉達が走り回る。
二人の会話を聞いていないふりをする。額に汗を感じる。
「え、というか佐藤、こいつってさ・・・」
僕は体が捻じ曲がるほどの電撃が体に走るのを感じた。痛い。こんな一瞬で全て失ってしまうのか。
「冷凍ビームじゃん、こいつやばいよ?」「なにそれ」
ああ、またあの苦しい日々に元通りだ、こんな簡単に崩れてしまうなら楽しさも知りたくなかったし、もう諦めて生きていくしかない。
でも思い切ってみようと思った。全く抗わずに奪われるのは違う気がする。
「場を凍らせちまうんだよ」「なんそれ」
「でもこのご飯すっごくおいしいよ!!」
自分から出た言葉が確実にずれたのを感じた。何を言ってるんだ、言いたいのはこんなことではないのに。
僕は感じた、いつものやつがくる。肌に刺さるような冷たい空気が。
「・・・ほらな?こいつの冷凍ビームだよ、これ」小声で佐藤に耳打ちしている。
僕は怖くて佐藤の顔を見れなかった。蔑んだような、嘲るような顔をしていたらどうしよう。動悸がする。
「解凍ビーーーーーム!!!!!!!」
佐藤が大きめの声で言った。
僕も、隣の彼も、佐藤以外は全員きょとんとしていた。
「な、これでいいじゃんね?お前も一緒に食うか?すげえうめんだよここ」
佐藤が彼に何もなかったように話をしている。彼は佐藤の全力にだんだん笑いながら、何か話を続けている。
ありがとう。ありがとう。僕は涙が出そうだった。変な返しだけれど、解凍ビームは聞いたことのない概念だけれど、佐藤の解凍ビームが今までの僕ごと救ってくれたような気がした。
佐藤にとっては何気ないユーモアだったのかもしれない。
冷凍するなら、解凍すればいいじゃん。なんだか違う気もする。でも僕にとっては人生で最高の技だよ。それは。
崖ぎわに捕まってもう落ちそうな僕を圧倒的な力で崖の上へ上げてくれた。
今正面の佐藤は、僕が今にも泣きそうで、さらに佐藤を命の恩人に思っているなんて、知らないんだろう。
僕のダメなところを見ても、呑気に定食を食べてくれてありがとう。
ありがとう、佐藤。ありがとう、解凍ビームを打ってくれて。
彼に電子レンジというあだ名がつき、セットでいじられるようになり、僕にもっと友達ができて、
佐藤への心からの感謝を佐藤の結婚式で言えたのは、これよりもまだ先の話だ。

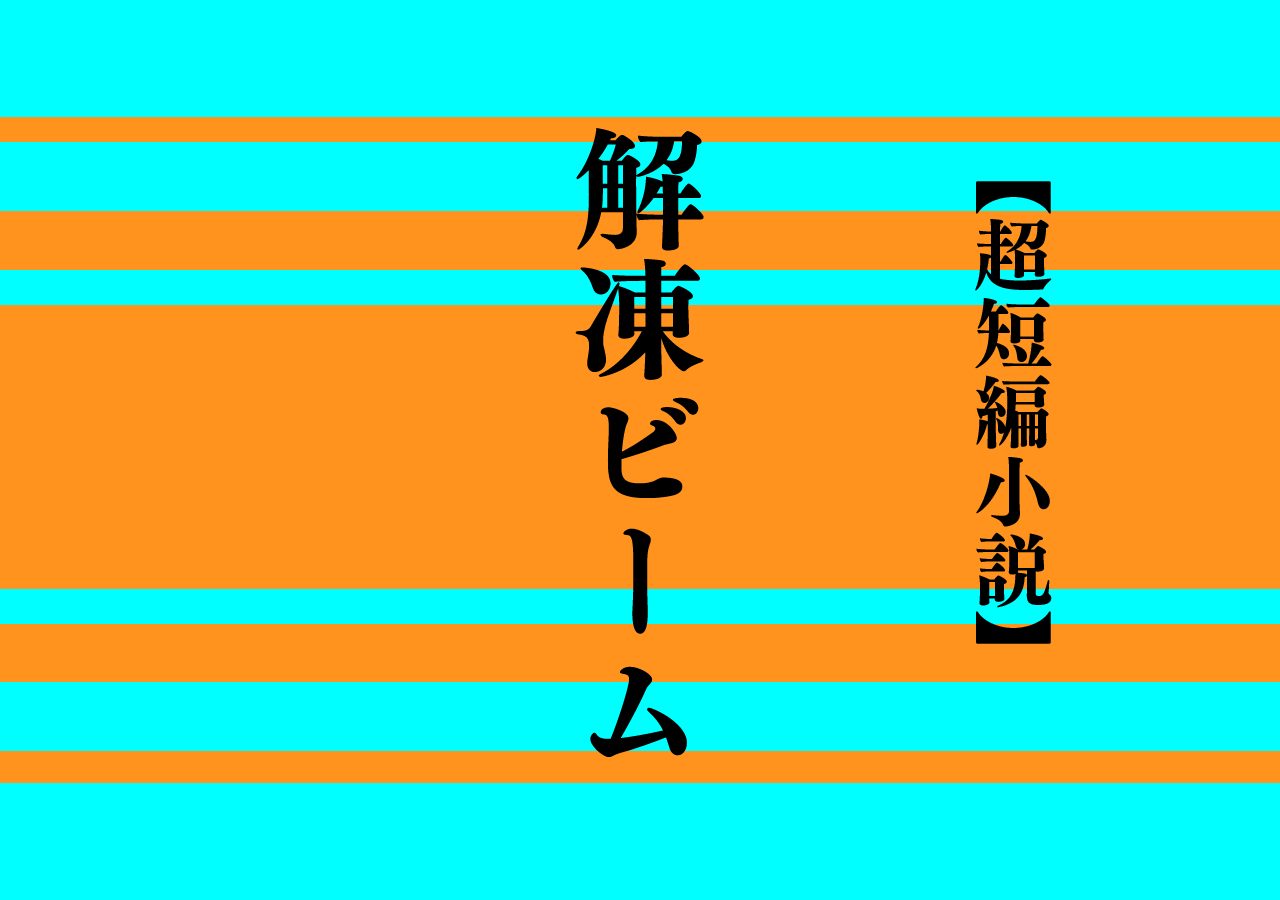
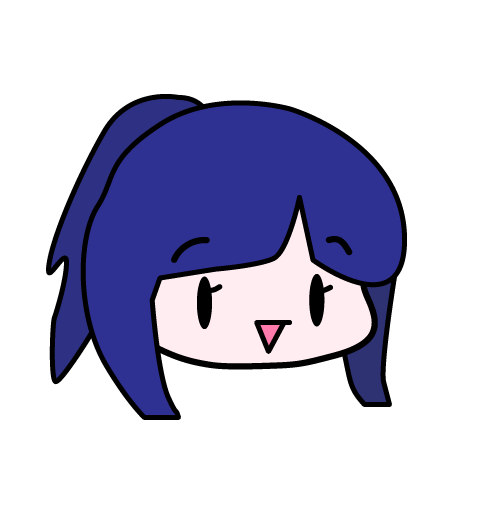

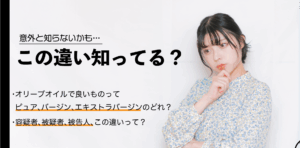



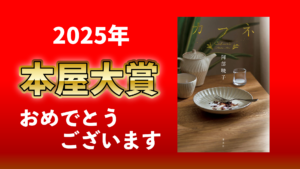


ご意見・感想待っているお